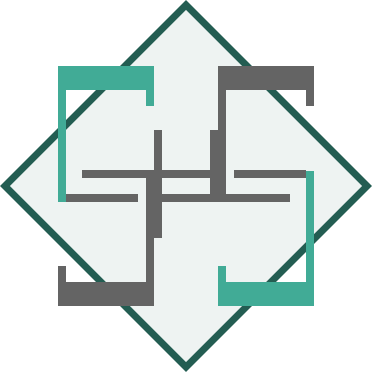決算期の変更はできる?
2025.09.20 更新
目次
決算月は自由に変更することが可能です。節税目的で変更する場合や繁忙期を避けたタイミングにしたい場合など、変更する理由も企業の都合で問題ありません。
しかし、決算月の変更には定められた手順を踏む必要があり、変えたいと思ってもすぐに変更できるものではないため、決算期の決定は慎重におこなう必要があります。
また、決算期の変更には次のとおりメリット・デメリットがあります。この後の解説で詳しくご説明いたします。
決算期変更に必要な3つの手続き
決算期を変更するためには、次の3つの順番に沿って手続きが必要となります。
- ①株主総会の開催
- ②定款の変更
- ③税務署への異動届と議事録の提出
①株主総会の開催
決算期変更にあたり定款を変更する際は、株主総会を開催して特別決議をとる必要があります。
株主総会には発行済株式総数の過半数を有する株主が出席し、そこで3分の2以上の賛成を得ることで「事業年度の変更」が成立します。
決議後には、決算期を変更する内容を記した「株主総会議事録」を作成します。
なお、親族で経営しているなど、規模が小さい会社の場合は、株主総会を開催せずに議事録を作成するケースが実務的にはほとんどかと思いますが、
議事録は税務署に届け出をする際に必要になるため、必ず作成しなければなりません。
②定款の変更
株主総会の特別決議後、定款の事業年度を実際に変更します。
定款の変更は公証役場での定款の認証や法務局での登記も不要ですので、費用はかかりません。
司法書士や行政書士に依頼すれば確実で手間を省いた手続きが可能ですが、コストを極力抑えたい場合は自社内のみで手続きを進めることをお勧めいたします。
③税務署への異動届と議事録の提出
定款の変更後、所轄税務署や都道府県税事務所、市区町村の役所や管轄の税務署に「異動届出書」を提出します。
異動届出書を提出する際は、決算期変更を決議した「株主総会議事録」のコピーを一緒に添付する必要があります。
各税務署等に届出書と議事録の提出をもって、決算期の変更手続きは完了です。法務局への登記申請は必要ありません。
その他、主要取引先や銀行などの金融機関にも、決算期変更する旨を連絡する必要があります。
届け出の期限
決算期変更の届出の提出期限は明確に定められていません。しかし、提出時期は「遅滞なく所轄税務署長に届出なければならない」とされているため、遅くとも「変更後」の納税月の末日までに提出するようにしましょう。
株主総会の特別決議は、変更後の決算月の末日までにおこないます。
たとえば決算期を3月から11月に変更したい場合、株主総会の特別決議の期限は11月30日になります。この場合、変更届出の提出期限は2ヶ月後の納税月の末日である1月31日までだと考えておく必要があります。
届け出が遅くなっても罰則はありませんが、早めの提出が求められているため2ヶ月以上遅れることがないようにしましょう。
決算期変更の4つのメリット
決算期を変更すると、主に次の4つのメリットが得られます。
- ・節税になる
- ・資金繰りを調整できる
- ・役員報酬変更のタイミングを早められる
- ・決算業務が楽になる
変更を検討するときに重要なポイントです。それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
節税になる
決算期の変更で得られるメリットで大きいものは、節税の効果が期待できる点です。
例えば、3月決算の会社が、3月に大きな売上がたち多額の利益計上が確定しているのであれば、決算日を2月に変更することで3月の売上・利益を翌期へ移動させることができます。
すると、今期の税負担を大幅に軽減し、翌期へ回した3月の売上・利益の納税は1年後にできるため、節税対策を立てて納税を下げることが可能です。
また、消費税の免税事業者である場合、決算期を変更することで、消費税の免税期間を延長できる可能性があります。
課税対象者となる基準は、1事業年度で売り上げが1,000万円以上(12カ月換算の必要有り)であることです。
1,000万円を超えた年度を基準として、翌々事業年度から消費税の課税事業者となります。
決算期前に、事業年度を通して1,000万円を超える売り上げの見込みがある場合には、事前に決算期を変更し免税期間を延長できます。
資金繰りが調整できる
申告納税の期限を資金繰りしやすい時期にできる点も、決算期変更のメリットとなります。
法人税・消費税は、決算月の2ヶ月後までに納税しなければなりません。
時期によっては売掛金が多く、現金預金が十分にないという場合も考えられます。決算期を変更することで、現金預金が潤沢にある時期に申告納税の時期を調整でき、無理のない資金繰りで納税することができるようになります。
また、期末の現金残高が多ければ、翌年度に向けて資産を購入したり、決算賞与を支給したりと、更なる節税対策も可能となります。
役員報酬変更のタイミングを早められる
役員報酬の金額は、新事業年度の開始から3ヶ月以内に株主総会で変更手続きをしなければなりません。
決算期を早めることで株主総会の時期も早めることが可能になり、役員報酬の金額も早期に変更できるようになります。
また、社会保険料対策として役員報酬を減額し、役員賞与で補填する方法も、決算月を早めることで早期に行うことが可能となります。
決算業務を余裕をもっておこなえる
決算期を迎えると、通常の業務と並行して決算業務も同時に進めていかなければならず、繁忙期と決算期が重なっていた場合、大きな負担となってしまいます。
また、決算期に決算書類や申告書を作成する他、決算予測や節税対策をおこなう場合には、税理士などとの打ち合わせが必要となってきますので、通常の業務が落ち着いている時期に決算期を変更することで、担当者は余裕をもって決算業務に集中できるようになるでしょう。
決算期変更の3つのデメリット
決算期の変更は、手続きが必要で手間がかかる以外にもデメリットがあります。
次の3つに注意が必要です。
- ・短期間での決算処理と納税が発生する
- ・前年度との財務データの比較が難しくなる
- ・税金の計算に調整が必要になる
それぞれ解説します。
短期間での決算処理と納税が発生する
法律によって、事業年度は1年を超えてはいけないため、決算期を変更する年度は通常より短い12ヶ月未満で決算業務をおこなわなければいけません。
短い期間で決算処理と申告が必要となりますので、それに伴い法人税・消費税の納税も早まることになります。
また、決算変更することで株主総会議事録の作成、定款変更、税務署への届出書の提出をしなければいけないため、変更時期は業務負担が一時的に増える可能性が高くなります。
決算業務が早まれば税理士に対する費用の支払いも早まるため、前年度よりも支出が増える月が発生することも留意しておかなければなりません。
前年度との財務データの比較が難しくなる
決算期を変更した場合、最初の事業年度は1年間より短くなるため、前年までの財務データとの比較が難しくなる点もデメリットとなります。
決算期変更前後では期間が異なるため、単純に損益計算書上の数字を比較しても業績の良し悪しの判断が難しくなってきます。
とくに繁忙月があったり、月によって売上の増減が大きい業種の場合は、より損益の比較が難しくなります。
税金の計算に調整が必要になる
前項でもお伝えしましたが、決算期を変更した場合、最初の事業年度は1年間より短くなります。
税法では、減価償却費の計算や中小法人などにおける軽減税率の適用、消費税の基準期間などは、12ヶ月の期間を想定しております。
そのため、主に以下の項目について、変更後の最初の事業年度だけは12ヶ月未満となるため月割換算での計算が必要となり、経費計上額や特例を受けられる金額が少なくなります。
- ・減価償却資産の償却限度額
- ・中小法人等の軽減税率適用
- ・消費税の基準期間の計算
まとめ
決算期は企業が任意に変更することが可能です。
そのため節税目的や自社の繁忙期を避けたり、納税月に合わせたりなど自由に変更が可能となります。
しかし、変更には時間がかかるため、決算月の設定は慎重におこなわなければなりません。
決算月の変更をする際は、社内で十分に検討したうえで計画的に進めましょう。
スタ-トアップサポート総合会計事務所では、お客様の最適な決算月や節税目的での決算変更等も積極的にご提案しております。
先ずはお気軽にご相談ください。