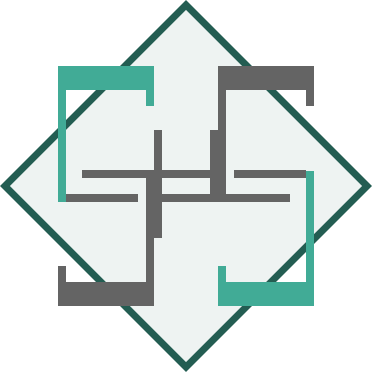個人事業主が税務調査で気をつけたいこと
2025.11.20 更新
目次
税務調査と聞くと「何を見られるんだろう」「どこを突っ込まれるんだろう」と不安になりますよね。
特に個人事業主の方にとっては、日常の支出と事業の支出の境目があいまいになりやすく、思わぬところで指摘を受けることもあります。
そこでこの記事では、税務調査でよく狙われる危険ポイント、事前にやっておくべき準備、当日の対応のコツ、そして最後に工夫(裏技)まで、順を追って分かりやすく解説していきます。
税務調査ってどんなもの?
「税務調査」と聞くと、なんだか怖いイメージがありますよね。
でも実際は、ほとんどのケースが「任意調査」といって、事前に通知が来て日程を調整して行われます。
脱税の疑いが強い場合に行われる「強制調査」とは違うので、まずは落ち着いて対応することが大事です。
税務署には「質問検査権」という権限があり、納税者には協力する義務があります。ただし、これは「何でも言うことを聞かなきゃいけない」という意味ではありません。
例えば、原本を持ち出す代わりにコピーを渡すとか、日程を調整するといったことは法律的に認められています。
要は「調査官の質問にきちんと答える」「必要な資料を提示する」ことが基本。逆に、無理に拒否したり隠したりすると余計に疑われるので、正しく準備して堂々と対応するのが一番です。
ここで知っておきたいのが、法人と個人事業主に対する税務調査の違いです。
法人の場合は、会社組織としての会計処理や内部統制がチェックされるため、調査の範囲が広く、数日間にわたることも珍しくありません。決算書や取締役会の議事録、役員報酬の妥当性など、組織的な観点から確認されます。
一方、個人事業主の場合は、事業と生活の境目があいまいになりやすいため、家事関連費の按分や売上の計上漏れ、交際費の扱いなど「日常の支出と事業の関係」を重点的に見られる傾向があります。
つまり、法人は「組織的な会計の正しさ」、個人事業主は「生活と事業の線引き」が調査の焦点になりやすいのです。
※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 調査対象 | 決算書、会計処理、内部統制、役員報酬、取締役会議事録など | 売上計上、経費の妥当性、家事関連費の按分、交際費の扱いなど |
| 調査期間 | 数日間に及ぶことが多い | 半日〜1日程度で終わることも多い |
| 論点の特徴 | 組織的な会計の正しさ、内部統制の有無 | 生活と事業の線引き、日常的な支出の妥当性 |
| 書類の種類 | 決算書類、契約書、議事録、社内規程など | 帳簿、領収書、請求書、家事按分の根拠資料など |
| 調査官の視点 | 会社としての仕組みが正しく機能しているか | 事業と生活をきちんと分けているか |
ちなみにここ数年の傾向として、税務調査に入りやすい業種は下記の通りです。
1位 経営コンサルタント
2位 ホステス・ホスト(ナイトビジネス)
3位 YouTube・ライブ配信者など
4位 金属くず卸売業
5位 ブリーダー(ペット関連)
自身の職種の傾向をあらかじめ掴んでおくことで、対策もしやすくなります。
調査でよくチェックされる「危険ポイント」
税務調査で狙われやすいのは、だいたい次のようなところです。
- 売上の計上漏れ
- 現金やQR決済、銀行入金の記録が帳簿と合っていないと「売上除外じゃない?」と疑われます。
- 経費の私的利用
- 通信費や車のガソリン代、家賃などを全部経費にしていると「これは事業じゃなくて生活費では?」と突っ込まれます。
- 交際費・会議費の線引き
- 飲食代を「会議費」として処理していると、業務目的がはっきりしない場合に否認されやすいです。
- 外注費と給与の区別
- 業務委託なのか、実質的には従業員なのか。ここを間違えると源泉徴収漏れを指摘されます。
- 在庫の棚卸
- 期末の在庫管理が曖昧だと、利益の計算が狂ってしまいます。
- 消費税の処理
- インボイス対応や課税・非課税の区分間違いもよく見られるポイントです。
つまり「売上・経費・源泉・消費税・在庫」このあたりが要注意。
ここをきちんと整理しておけば、調査官も納得しやすいんです。
調査前にやっておくべき準備
「調査が来てから慌てる」のではなく、普段から準備しておくことが大切です。
- 帳簿と証憑のひも付け
- 仕訳ごとに領収書や請求書を紐づけておく。フォルダ整理も「年度→月→科目」で検索しやすく。
- 家事按分のルール化
- 自宅兼事務所なら、面積や使用時間で割合を決めて毎年同じ基準で処理。
- 売上管理の一本化
- 現金・カード・QR決済を全部まとめて台帳に記録。銀行入金と照合して「漏れなし」を証明できるように。
- 外注契約の整備
- 業務委託契約書を作っておくと「給与じゃない」と説明しやすい。
- 棚卸の見える化
- 期末に在庫表を作り、写真も残しておくと説得力が増します。
要は「聞かれたらすぐ出せる状態」にしておくこと。
これだけで調査のストレスはぐっと減ります。
調査当日の対応と法律的に問題ない工夫
当日は「論点を絞って、証拠で説明する」ことが大事です。
- 調査範囲を確認する
- 最初に「どの年度・どの論点を調べるのか」を確認してメモに残す。
- 原本は持ち出させない
- コピーやデータで対応すればOK。原本は事業者が保管するのが基本です。
- 説明は図や表で見せる
- 売上の流れや按分の計算は、紙や画面で見せると一発で理解してもらえます。
- 修正申告は慎重に
- 勧められてもすぐに応じず、根拠を確認して納得できる範囲で対応しましょう。
- 税理士の同席
- 事実関係は自分が答え、法律的な評価は税理士に任せるとスムーズです。
これらは「裏技」というより、法律的に認められている正しい工夫です。調査官も仕事がしやすくなるので、結果的に調査時間も短くなります。
なお、判断が曖昧な場合はその場ですぐに返答せず、「後程税理士に確認して返答します」等のように伝えることで誤解を招く言動を防ぐことが可能です。
普段からの運用が一番の防御
調査は「過去の数字」を見るものですが、評価されるのは「今の運用がちゃんと続いているか」です。
- ・記帳や証憑保存のルールを文書化しておく
- ・毎月のチェック項目を決めて、漏れがないか確認する
- ・家族や税理士など「第三者の目」を入れてダブルチェックする
- ・年末に「税務リスクチェックリスト」を作って自己点検する
こうした運用を続けていれば、調査官も「この人はちゃんとやっている」と判断してくれます。
まとめ
税務調査は「怖いイベント」ではなく「日頃の整理を見直すチャンス」です。
危険ポイントは売上・経費・源泉・消費税・在庫に集中していますが、事前準備と当日の対応をきちんとすれば、調査はスムーズに終わります。
そして一番大事なのは「普段からの運用」。帳簿や証憑を整理し、ルールを決めて継続することが、調査に強い個人事業主になる秘訣です。
スタートアップサポート総合会計事務所では、税務調査の立ち合いも行っておりますので、ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。